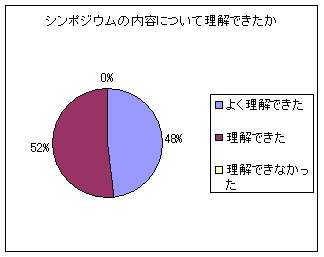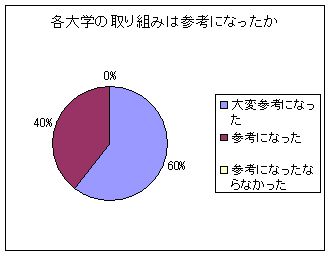|
国立大学法人奈良教育大学特色GP(平成15年度採択事業)
|
| 日時 平成18年12月9日14:00〜17:00 場所 奈良教育大学 大会議室 プログラム 学長挨拶 14:00〜14:05 本学の取り組み紹介 14:10〜14:45 シンポジウム 15:00〜16:50 副学長挨拶 16:55〜17:00 |
 ※ 多数のご参加のうちに、終了いたしました。 ありがとうございました。 |
【実施報告】
1.シンポジウムの成果
3年間の特色GPプロジェクトの本学の取り組みの成果発表と各シンポジスト所属大学の取り組みの
紹介及び意見交換を通じて、導入教育、教養教育のあり方並びに学生支援のアプローチに関し参加者
の理解を深めることができ、参加者アンケートには、教育のあり方や教育課程を考える上で参考にな
ったという意見が多く寄せられました。
2.今後の事業への反
シンポジウムの発表と意見交換から、各取り組みを実施する大学教員の共通認識と共同体制が事業推
進の重要な要素となるとの認識が確認されました。今後は、実施内容とともに共同体制の充実を企図
して、取り組みに活かしていく予定です。
3.参加者数 55名(大学関係42名、学生8名、一般5名)
|
奈良教育大学の取り組み・成果発表 |
|
|
奈良教育大学 森本弘一教授
導入科目群の学習支援が4年間にわたりどのように展開されてきたか、授業の
映像や学生評価を取り上げながら紹介。4年間の取り組みが、導入科目群に携わ
る教員の組織力を高め、そのことが学生の授業満足度に反映されたことに言及。
|
シンポジウム 特色GPの学生支援に果たす役割 |
|
|
コーディネーター 上野ひろ美教授 |
|
|
|
|
|
シンポジスト 安藤厚先生(北海道大学 文学研究科 教授) 北大は「進化するコアカリキュラム」と銘打ち教養科目の改善を図っている。1学年2600人を数える大学の規模は、全学協力のよさと問題点を提示している。私どもを支えているのはクラーク博士の理念であり、フロンティア精神、実学の重視などの観点から少人数の演習形式を用意している。 |
|
|
|
|
|
シンポジスト 芝井敬司先生(関西大学 副学長 文学部 教授) 学生28000人7学部11研究科の本学では改革は並大抵のことではない。本学の「人間性とキャリア形成を促す学校インターンシップ」では、文学部として外部と連携することを目ざした。特色GP採択後には高大連携推進室を立ち上げ、高等学校へ学生を派遣するといった事業を行っている。 |
|
|
|
|
|
シンポジスト 松木健一先生(福井大学 教育地域科学部 教授) 教員養成系学部は今後学部教育と現職教育の地域総合センターとしての存在に再生さねばならない。そのためにも教師の専門性を明示する必要性があり、理論と実践をつなげる取り組みを行っている。(ライフパートナー(地域と協同した不登校児支援)、eポートフォリオなど) |
|
|
|
|
|
シンポジスト 岡部善平先生(小樽商科大学 商学部 助教授) 大学の中だけで学生を育てるのが難しい現代にあって、本学は高1から社会人3年後までを見通した教育支援を行っており、現場との連携に努めているが、残念ながらGP採択には至っていない。今日のシンポを聞き、組織作りと地域連携の重要さに改めて思い至った。 |
|
シンポジウム会場から |

(柳澤学長による開会挨拶)

(授業の動画記録をもとに発表する森本教授)
|
シンポジウム参加者アンケートから |