-「考える力」「表す力」の育成をめざした教育者養成-
(1)取組の背景、概要について
①大学の基本目標
単科教員養成大学である本学には、「学校教育教員養成課程」と「総合教育課程」の二
課程を設置している。学校教育教員養成課程では初等中等学校教員の養成をめざし、総合
教育課程では生涯学習社会における教育の多様なニーズに対応する専門的職業人の育成を
図っている。両課程に共通した目標は、有能な教育者の養成にあり、中期目標・計画にも
その趣旨を掲げ、目標達成に取り組んでいる。
②教育の現代的課題に対応する力の形成と導入教育
有能な教育者養成をめざし、4年間のライフコ-スを図のように設計している。
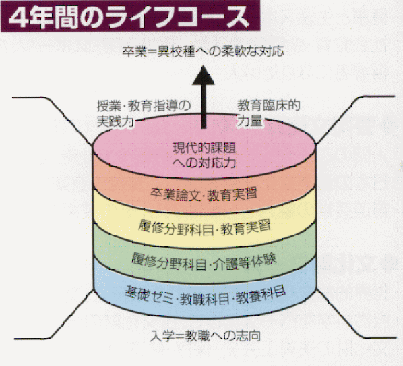
1年次に基礎ゼミナール、教養科目、入門教職科目を手厚く配置し、2年次・3年次の
専門教育を経て、4年次の卒業論文をもって学士課程の完成に至る。その際,1年次から
4年次まで貫かれるのは教育の現代的課題に対応する力を培うことである。
本学に入学してくる学生は教育者としてのプラス面のみをイメージして育ってきた学生
が多く、社会や学校の現状に対する問題発見能力、現代的課題に批判的に対応し得る判断
力や行動力が十分に育っているとはいい難い。その点を強く自覚し、初年次から、現代的
課題への対応力の育成に寄与する導入教育に重点を置いている。なかでも、高等学校まで
の被教育体験のなかで,正しい答えを所与のものとする受け身的な学習の構えが定着してい
る現状に対して、学び方を学び、友人や教員とともに学びの共同体を形成し、そこで心お
きなく自己の考えを披瀝して対話や授業討論に及ぶコミュニケーション能力を、現代的課
題への対応力として位置づけている。
③導入教育科目群の新たな設置
本学では専門教育もまた教養的・基礎的内容を併せ持つと捉え、専門性を視野に入れた
教養教育科目として導入教育科目群を設定している。とりわけ新たな使命を担って開始さ
れたのが、「学校教育基礎ゼミナール」「総合教育基礎論」「総合教育基礎ゼミナール」
「情報機器の操作」「現代教師論」で、入学したてのすべての学生が必ず受講する。
「学校教育基礎ゼミナール」は、学校教育教員養成課程の1回生全員を対象としたディ
ベートを軸にした演習型の体験的授業の試みであり、「総合教育基礎論」は、総合教育課
程の1回生全員が入学直後の半年間にわたり一堂に会して受講する、教育の現代的課題に
対する問題意識を培う入門的授業である。この2つを中心として「総合教育基礎ゼミナー
ル」「情報機器の操作」「現代教師論」などがこれを補完している。
(2)取組の内容について
導入教育科目群の構造は下図のとおりである。社会や教育の諸事象について、仲間や教
員との授業対話を通して「考える力」「表す力」を鍛え、学習意欲や学びの共同体を構築
していくのが導入科目群の役割である。その中心となる取り組みについて述べる。
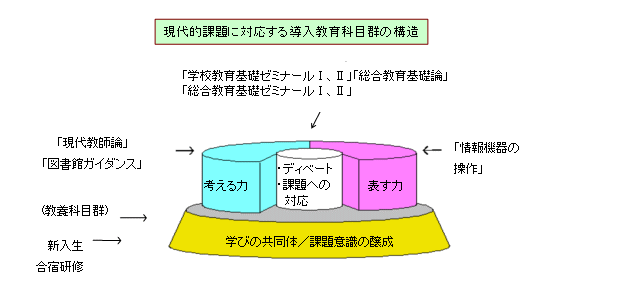
①「学校教育基礎ゼミナール」
「学校教育基礎ゼミナール」は学校教育教員養成課程の1回生全員を対象としたディベ
ートを軸にした演習型の体験的授業である。ディベートにより現代的課題に対する問題意
識、論理的思考力、表現力、組織力を育成し、専門教育科目と教職専門科目への意識づけ
を図る。現代的課題への対応力の育成を目標に掲げ、3つのねらいを定めている。
ア)知的なものの見方や考え方の基礎を養い、その有効な表現方法について学ぶ。
(事実に基づいた発言、論拠の提示、データの収集方法等)
イ)ディベートを通して、学校教育をめぐる諸問題について多面的に考える。
(教室ディベートのスキル習得、現代における教育問題の考察)
ウ)学生と教員、学生と学生の相互学習の時間と空間を創造する。
(「対話カード」を通した学生と教員による双方向学習の場の創出)
【論題】は多彩である。「小学校の運動会の徒競走での順位付けは不要である」「殺人
を犯した少年には大人と同じ刑事責任を問うべきである」等の論題の是非を問う。
【授業形態】は演習形式で、全体学習とグループ学習の交互転換を図っている。基礎・
基本に関わる講義と演習は全員を前に実施し、次いで約40名のグループに分かれてディベ
ートを行う。さらに、全体場面で、グループ対抗あるいは、学生が所属する専門性に基づ
くグループ(コース)対抗のディベート大会を行う。学生は全員が参加し、大会が実施さ


「ディベート大会風景」 「作戦タイムでの相談」
れる旨は学内全体に広報され、次年度担当教員や興味をもった教員が集まる。学生は、出
来映えに関わらず体験的・ゲーム的要素により自己活動を惹起されている。
指導は【TT(ティーム・ティーチング)体制】をとっている。学校教育教員養成課程は
4つのコースから構成されるが、入学時展開の導入教育を重視する意味で、それぞれのコ
ース担当の教員を指導陣として配置している。毎年、専門の異なる9名の教員が協同指導を
展開し、また教員と学生、学生と学生が入学直後に相互を身近に知る機会として相互交流
を活発化させている。ディベートに関する専門家を招き、教員のための講習会をもったり、
また、教員研修の一環として、学生の前で教員が実際にディベートを実演したりすること
もある。後者の活動は学生に与えるインパクトが大きく、関心を高める一助となっている。
オリエンテーションからディベート大会に至る15回に及ぶ授業を、9名のTT体制で実
施するためには、緻密な打ち合わせと役割分担が欠かせない。そのために担当教員は毎週、
昼休みを利用して周到な打ち合わせを重ねている。大人数を対象とした体験的授業を展開
するという教育負担を担いつつ、教員がTTを楽しんでいるのもこの授業の特徴といえよう。
②「総合教育基礎論」
「総合教育基礎論」は総合教育課程の1回生全員が一堂に会して受講する、教育の現代
的課題に対する問題意識を培う入門的授業である。環境、文化、情報、健康、エネルギー
等の問題と関わらせた総合教育の課題に取り組むなかで、《思考力・表現力・行動力・想
像力》の4つの力の獲得をめざしている。
【授業形態】は講義形式である。学生に対し、知的刺激を与えたり不思議と思う心を喚
起したりして学問への動機付けとする。また、現代社会の今日的な諸問題についての考察
を深めるため、問題解決に向けた新しい視点及び方法論を提供する。教員と学生は共同探
求の徒となる。
指導は【TT体制】をとっている。総合教育課程の各専修の教員が授業担当者となり、テ
ーマを設定して、一貫性とまとまりのある内容としている。テーマは例えば「生涯学習に
おける諸問題を考える」「文化財が語るもの」「高度情報・先端科学社会の諸問題」で、
学外講師をも招聘しながら展開する。
この取り組みでは【学内外との連携】をも視野に入れている。毎回、NPOや経済界等、地元
地域から学外講師を招き、体験談を聞く。大学における授業の在り方について討論会をも
つこともある。また、TT体制を組んでいる教員以外にも、関心のある教員は自由に聴講参
加できるようにしているため、教員相互の啓発機能、FD(ファカルテイ・ディベロップ
メント)の機能をも果たしている。
③その他の授業科目等-「情報機器の操作」「図書館ガイダンス」「新入生合宿」等-
「情報機器の操作」「図書館ガイダンス」は、入学当初のガイダンス科目として各授業
での「調べる力」や発表力育成を図っている。また入学直後に新入生合宿を実施し、共同
体での学びへと動機付けている。さらに、「学校教育基礎ゼミナールⅡ」「総合教育基礎
ゼミナールⅠ・Ⅱ」で内容的接続を図り、「現代教師論」では小学校、中学校、幼稚園で
の教育実践の観察参加をおこなうことを通して、子どもや教育に対する関心と問題意識の
醸成を図っている。
(3)組織的対応について
①教務委員会と連携した運営
冒頭に述べたように、導入教育科目群の設置は、平成11年学部改組に伴い、改組準備委
員会を中心に組織決定されて出発したものである。改組を終えた後の運営は、教務委員会
がその総括にあたっている。
例えば「学校教育基礎ゼミナール」の場合、授業担当者は、学生の学習支援上の担当者
(本学では「学年担当教官」と称している)があたることを原則としている。学生が所属
する各コースから選出された9名の教員が一つのチームとなり、平成15年度までの5年間で
のべ45名の教員が担当してきた。毎年担当者が変わるわけであるが、これをカバーするた
めに、毎年度末にその年の担当者から次年度担当者への引き継ぎを行い、次年度担当者は、
新年度第1回目の授業が始まるまでに、数回の打ち合わせ会をもつ。担当教員のために学外
講師による研修や実際のディベート練習が実施されることや、あるいは前年度担当者によ
る研修や緻密なオリエンテーションがもたれることもある。
「総合教育基礎論」は、立ち上げ当初より有志教員によるプロジェクトチーム等によっ
て意欲的で周到な研究や準備が重ねられ、現在では、「学校教育基礎ゼミナール」と同じ
く、教務委員会が運営の総括を担っている。
いずれの場合にも、課題や懸案は担当教員間で話しあわれた後、教務委員会で検討され、
その支援を受けて解決される。
さらに、特徴的なこととして、各年度の実践内容を収録した報告書の作成がある。これ
はひとえに担当教員集団の熱意によるものである。平成11年に出発して以来、毎年、詳細
な報告書が作成され、大学の名において学内外に広く配布されている。報告書作成にあた
っては、予算の確保のみならず、事務サイドの協力が組織的に実施されている。
【予算の獲得】については、「教養教育改善充実特別経費」「教養教育特別講義プログ
ラム推進経費」「学長裁量経費ー教育研究改革・改善プロジェクト経費」等によるプロジ
ェクトを編成して獲得している。前年度担当者チームが申請をおこない、次年度の準備に
あたる。講師招聘による成果、他大学見学による情報、ディベート研修図書等は年度に渡
って活用され、何よりも上に述べた、毎年作成される報告書が、次年度の教育実践に生か
される点が大きい。以下に掲げる。
・『「学校教育基礎ゼミナールⅠ」の取り組み -成果と課題-』 H.11
・『学校教育基礎ゼミナールの展開 -基礎ゼミⅠ ディベートを中心に-』 H.12
・『ディベート学習に取り組んで』 H.13
・『新機軸へ向かう奈良教育大学』 H.11
・『新生 奈良教育大学の胎動と音色』 H.12
・『「総合教育基礎論」と奈教の明日』 H.13
・『《総合教育課程》における総合教育の実践 -自分で考え、理解し、行動すると
はどういうことか』 H.14
(4)取組実績について
平成11年度より取り組みを開始し、取組実績は平成17年度で年度で7年目を迎えた。
①教育効果
FD委員会でとっている平成13-14年度の【授業評価アンケート】によれば、【演習型・体
験型授業】の「学校教育基礎ゼミナール」に関する結果は以下のようである。「予習・復
習」について、平成13年度においては、「3時間以上 14%、2時間程度 15%」であった
が、平成14年度においては「3時間以上 26%、 2時間程度24%」と予習・復習の時間が
延びている。また、「受講して、関連する学問領域や研究分野に興味を覚えた」では、平
成13年度においては「覚えた 30%、ある程度覚えた 51%」であり、平成14年度におい
ては「覚えた 25%、ある程度覚えた 51%」で、約8割の学生が興味をもったとしている。
さらに「授業に自主的かつ意欲的に取り組んだ」が平成13年度92%、平成14年度79%で、
「新しい知識や考え方を知ることができた」が平成13年度92%、平成14年度 87%、「教育
実践の新たな知見を得ることができた」 が平成13年度91%、平成14年度82%と続き、高い
数値を得ている。論議のなかでテーマを設定し、必要な資料を収集し、論点を定めて思考
し、議論を進める等、問題発見力や自ら学ぶ力が形成され、ねらいに適合した結果を得て
いるといえる。
以下は【学生の感想】の一端である。「我がコースが決勝戦に出られてよかった。皆団
結してがんばったと思う。この基礎ゼミを通じて、考え方、話し方、聞き方などを学ん
だ。」「学校生活で日常的に疑問視される身近な問題を皆で考えることができたのでよか
った。身近なことの方が自分の考えを主張しやすく、また他人の違う考えにも賛同できる
点もあるので面白かった。」「論題が難しくなればなるほど下調べなしではディベートで
きず、論理的に話す必要性があると思った。」
【講義型授業】の「総合教育基礎論」に関する授業評価アンケートでは、以下の結果を得
ている。「受講して、関連する学問領域や研究分野に興味を覚えた」とする学生が平成13
年度、14年度ともに 81%あり、教育目標が達成されている。「新しい知識や考え方を知る
ことができた」が平成13年度78%、平成14年度72%と高い評価を得ている。
②【共通性、公共性等について】
導入教育をどのような授業科目に連携させて展開するかについての試みとして、その中
核にディベートによる授業を据えたことは、教育効果をあげている。この点については、
大学評価・学位授与機構による評価報告書「平成12年度着手継続分/全学テーマ別評価『教
養教育』」における「3.教育方法」欄で、「授業方法の工夫として、ディベートやディス
カッションを用いた授業、ロールプレイやペアワーク等の導入など、新しい試みも取り入
れ、多彩な方式で実施しており、特に優れている」という評価を得ている。
また、取り組みのもう一つの核である講義型の「総合教育基礎論」についても、入学し
たての学生に、狭い専門に分化されない多様な分野からなる、共通テーマに基づく講義を
展開することは、大学教育への導入として試みられるべきものである。
本学の取り組みが学生の【社会性の涵養等、公共性】に寄与できたかを問えば、その成
果には以下の点をあげることができる。
・説明責任、情報化社会におけるプレゼンテーション力の育成等、教育の現代的課題に
応えることができている。
・環境・文化財・世界遺産等、地域の身近な問題をとりあげているので、学生の社会
的教育的問題に対する心構えや判断力の涵養に寄与している。
・受動的な学びになれてきた成長過程、他者との応答のなかでの自己形成が困難にな
っている現代の青年の発達課題に積極的に応えることができている。
・とりわけディベートでは、論理的思考力や表現力は勿論、次の教育効果が期待でき、
社会性の涵養に適している。①組織の一員として組織に貢献する態度の育成 ②情報
活用能力の育成 ③「社会的振る舞い」の育成
以上は「現代的課題に対応する導入教育科目群の展開」についての取組内容、実施組織、
実績等を平成15年度までの取組みをベースに記述したもので、その後の取組みの内容、評
価については、平成18年度中に取りまとめ、報告を予定している。