奈良縣師範學校附属小學校 児童文集「わかくさ」の解説
増田 信一 奈良教育大学元教授
(現職時: 国語教育・教授)
奈良縣師範學校附属小學校 児童文集「わかくさ」の解説
増田 信一 奈良教育大学元教授
(現職時: 国語教育・教授)
我が国で文集指導が盛んになったのは大正時代の始めのころのことである。大正時代に なって、自由教育の機運が高まってくるに連れて、考えたことを自由に綴る作文活動が盛 んになりだした。大正7年から始まった、鈴木三重吉の月刊雑誌「赤い鳥」はその代表的 な存在である。
「赤い鳥」と同じころに、本学の前身である奈良師範附属小学校の学校文集「わかくさ 」の出版が始まった。惜しくも第1号と第2号は散逸してしまい収集することができなか ったが、第3号から後の号は資料館で収集することができた(ただし、現物は当館には不在)。 ここでは、第3号から30号までの本文を紹介することにする。
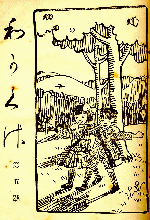
| 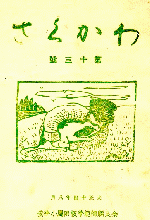
| 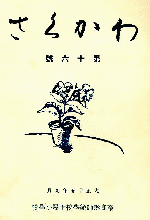
|
なぜ30号まででとどめたかというと、昭和期に入ると不景気の傾向が強まり、戦争体 制を整えるための締めつけが強くなったために、作文教育が低調になったからである。 この間の事情については、本教育資料館ビデオ(VHS方式)「文集からみた奈良県の作文教育」 (1994年度制作)に詳しく述べてあるので、合わせてご覧いただきたい。
この文集は年に2回ないし3回発行され、ページは40ページ前後である。なお、1号 から26号までの文集名は平仮名の「わかくさ」であるが、27号から後は漢字が使われ たり平仮名が使われたりしてまちまちである。
奈良女子高等師範学校附属小学校で出版した月刊雑誌「伸びて行く」の創刊は大正10 年のことであるから、同じ時期に「わかくさ」が出版されたわけである。(第1号が収集 できなかったので創刊の正確な日時は不明である。)
各号の構成はほぼ決まった形式を取っており、「説苑」3・4点、「学校通信」3・4 点、「児童作品」20〜30ページ、という3部構成になっている、ここでは第3号から 30号までの全文を掲載しているから、その具体を実際にご覧いただきたい。
全国的に見ても、大正時代にこれだけの文集が継続して発行された例は少ないから、こ こに載せた「わかくさ」の持つ意味は大きい。第1部の「説苑」の内容は、教師の文章だ けではなく父母の文章もかなり見られ、大正時代の自由主義教育をもっと推進しようとす るものや教育制度そのものを改革しようとしたものが多い。また、第3部の「児童作品」 は子どもたちの素直な感覚によって表現されたものが多く、明治末期から大正期にかけて 話題となった形式主義的な色に染まった作文は見当たらない。
大正時代に、我が附属小学校では、形式主義作文にとらわれない自由で伸び伸びとした 作文教育がなされていたことを、うかがい知ることができる。(奈良教育大学 国語教育・教授 増田 信一)
(03) 第 三 号 (大正十一年 )
(04) 第 四 号 (大正十一年七月)
(05) 第 五 号 (大正十一年十二月)
(06) 第 六 号 (大正十二年三月)
(07) 第 七 号 (大正十二年七月)
(08) 第 八 号 (大正十三年一月)
(09) 第 九 号 (大正十三年五月)
(10) 第 十 号 (大正十三年九月)
(11) 第 十一 号 (大正十四年二月)
(12) 第 十二 号 (大正十四年四月)
(13) 第 十三 号 (大正十四年八月)
(14) 第 十四 号 (大正十五年一月)
(15) 第 十五 号 (大正十五年五月)
(16) 第 十六 号 (大正十五年九月)
(17) 第 十七 号 (昭和 二 年一月)
(18) 第 十八 号 (昭和 二 年六月)
(19) 第 十九 号 (昭和 二 年九月)
(20) 第 二十 号 (昭和 三 年一月)
(21) 第二十一号 (昭和 三 年六月)
(22) 第二十二号 (昭和 三 年九月)
(23) 第二十三号 (昭和 四 年二月)
(24) 第二十四号 (昭和 四 年四月)
(25) 第二十五号 (昭和 四 年九月)
(26) 第二十六号 (昭和 五 年一月)
(27) 第二十七号 (昭和 五 年四月)
(28) 第二十八号 (昭和 五 年九月)
(29) 第二十九号 (昭和 六 年一月)
(30) 第 三十 号 (昭和 六 年四月)