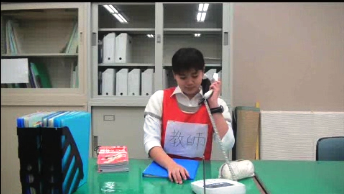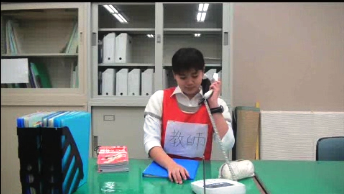
学校での児童のケガは、頻繁に発生する。担任や養護教諭は、その都度機敏かつ適切に対応しなければならない。とくに首から上のケガ(頭、目、歯など)では、必ず医師や歯科医師の診断を受けさせる。初動がその後を大きく左右するケースもある。
このケースの場合、担任は電話を受けた時点で自分のミスに気づいたと思われる。担任にはケガの対応を誤ったこと、保護者への連絡を怠ったことの両方に落ち度があった。担任は、この電話の後、校長または教頭に経緯を報告し、すぐに家庭訪問する。父親の来校後の説明では、対応が後手に回ることになる。家庭訪問で、父親には担任が把握した状況を報告し、自分の対応に2点にわたって落ち度があったことを謝罪する。弁解は不要であるばかりか、解決をますます困難にする。このような家庭訪問や対応に教頭や学年主任の同席を求める教員がいるが、保護者の目にはさらに頼りない担任と映る。いくら若くても、経験が少なくても、自分の落ち度は自分で解決するという心構えが必要である。
児童のケガの内、頭、目、歯などのケガでは、養護教諭などの判断を経て医師や歯科医師の診断を受けさせる。緊急を要するケガでは、救急車を呼ばなければならないこともある。学校では、職員室や保健室に近隣の専門医院(内科、外科、眼科、耳鼻科、歯科など)の連絡先を掲示する、必要なときに保護者へ緊急連絡ができるよう連絡先を一括管理する、教職員の誰もが緊急対応できるよう研修を積む、など緊急のケースに備えなければならない。また、子どもが学校でケガをしたときは、ケガの大小にかかわらず、「今日○○のケガをしました。学校では○○の処置をしましたが、家でも様子を見てやってください。」などと、そのケガの状況に応じて家庭訪問、電話、連絡帳などで保護者に連絡する。学習指導、生活指導、校務分掌の仕事に忙殺される学校では、このケースのようなミスは誰にでも起こり得る。学校でのケガでは、ケガの大きさではなく、その時の初動の是非が大きな問題に発展するか否かを決定する。