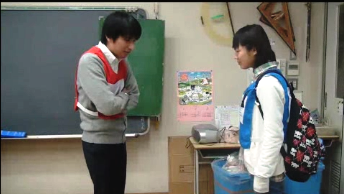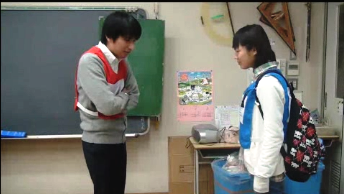自分の見解とファシリテーターの解説には、どのような違いがありましたか?
教師力サポートオフィスではこのほかにもたくさんのケースを用意し、
対応力を養うための取り組みも行っています。
小学校の低学年の場合、下靴を本人が間違って別の場所に入れたという可能性もある。しかしこのケースは6年生であり、本人の間違いではない。このようなケースでは加害者が特定されないことも多く、しかも加害者は同じ学級、被害者の友達など身近な者の場合も多い。そのため、当該児童には靴がなくなったという事実以上の心理的打撃があり、担任はこのことに留意しなければならない。また、担任の動きは「靴を隠す」という加害者の行為がこの女子児童を狙ったものであるのか、たまたまこの女子児童であったのかで異なる。
その場で下足箱周辺を探し、見つからなければ当該児童から当日の状況を時系列に沿って聴取し、上靴などで下校させる。児童を少しでも安心させるため、「先生は、できるだけのことをする。」という言葉を添えるとよい。その後担任は、当日及び明日以降の対応を決定し、家庭訪問の上、「明日朝、職員打合せ等で当該児童の靴がなくなったことを連絡し、たくさんの先生の目で探してもらいます。」「学級ではこのたびの経緯を話し、全員で靴を探します。」などと、保護者に伝える。
次の日、職員打合せ等でこのケースを報告し、最近同様のケースが起こっていないか、ほかの教員に心当たりはないかなどの情報提供を呼びかける。また、学級では、このたびの経緯と再発防止のための講話を行う。講話は「被害者は大変困っている。」「不注意で間違えたのなら申し出てほしい。」「どこかで見つけたら教えてほしい。」「次の休み時間、学級全員で探そう。」など、その学級の状態にもよるが、この講話は、加害者が聴いている場合が多く、再発を防止するためにも内容を吟味しなければならない。
靴が見つかっても、トイレの便器に投げ込まれていた、落書きされていた、カッターで切られていたなどの場合は、明らかにこの女子児童を狙っての嫌がらせであり、加害者発見まで指導を継続しなければならない。
CASE3.子どもの靴がなくなった
【ファシリテーターの解説】
教師力を育むケースメソッド18
Copyright(c)2010-2012 Teachers' Competency Model Development Project, NUE,
All Rights Reserved.