|
なまえ(和名)
|
シラホシカメムシ |
|
なまえ(学名)
|
Eysarcoris ventralis |
|
いろ
|
体(からだ)はうすい灰色(はいいろ)がかった茶色(ちゃいろ)で全身(ぜんしん)に小(ちい)さな黒い(くろい)点がある。 |
|
きせつ
|
4がつ〜11がつ |
|
なかま
|
カメムシ目 カメムシ科 |
|
おおきさ
|
5〜7 mm |
|
すみか
|
イネ科の植物(しょくぶつ)がはえているばしょにおおい |
| くわしいせつめい |
| エノコログサなどのイネ科(か)の植物(しょくぶつ)によくつきます。シラホシカメムシがイネの穂(ほ)から汁(しる)を吸(す)うと斑点米(はんてんまい)ができる原因(げんいん)となるため、イネの害虫(がいちゅう)とされています。マメ科(か)やキク科(か)の植物(しょくぶつ)にもつきます。
背中(せなか)に小(ちい)さな2つの点(てん)をもちます。 トゲシラホシカメムシに似(に)ていますが、トゲシラホシカメムシは背中(せなか)の左右(さゆう)にでっぱりがあるので、シラホシカメムシとみわけることができます。 北海道(ほっかいどう)・本州(ほんしゅう)・四国(しこく)・九州(きゅうしゅう)・沖縄(おきなわ)でみつかります。 成虫(せいちゅう)の姿(すがた)で冬(ふゆ)をこし、春(はる)になると活動(かつどう)をはじめます。 |

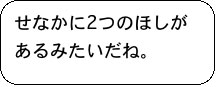
|
シラホシカメムシ
|
 |