- ステージ:ライドグラスをのせる所
- 固定用クリップ:スライドグラスをステージに止めるもの
- ステージ操作ねじ:ステージを動かすねじ
- フォーカス調節ねじ:フォーカスをあわせる
- 鏡筒(きょうとう):カガミが入っていて、光を反射させています。
- 接眼レンズ:目で見るところ
- 対物レンズ:見たいものに近づくレンズ
- レボルバー:対物レンズをはめる所、回転する。
- しぼり調節ねじ:光の量を調節するしぼり
- しぼり芯出調節ねじ:光の位置を調節するねじ
接眼レンズも対物レンズも、けんびきょうから取りはずせます。
接眼レンズは、鏡筒(きょうとう)にはめてあるだけです。
対物レンズはだいたいの場合、ねじ式になっています。 いろいろな倍率の対物レンズがはまっています。
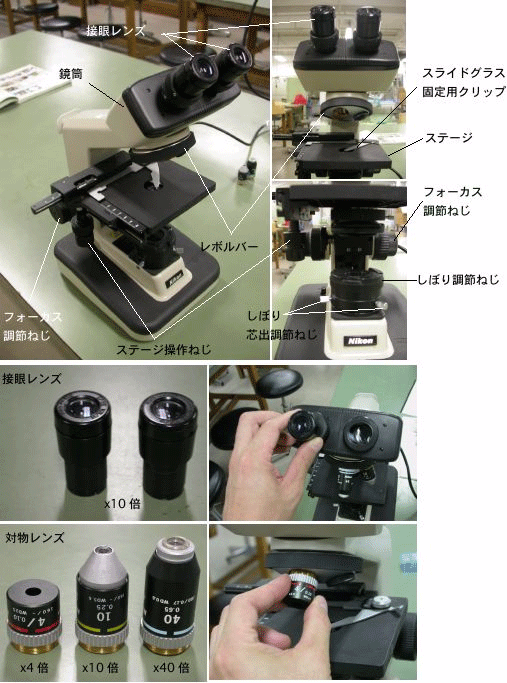
フォーカスをあわせるとは、ぼやけて見えない状態から、きれいに見えるようにすることです。右の図を見てください。
- まずは、フォーカス調節ねじを使って、ステージを対物レンズぎりぎりまで近づけます。このときは、ステージに顔を近づけて見てください。
- 次に、接眼レンズをのぞきながら、フォーカス調節ねじでステージを下げてゆきます。こうすると、スライドグラスに当てないで、フォーカスをあわせる事ができます。
- 一番左の図は、実際にどのように見えるかを示しています。フォーカスをあわせてゆくと、ぼんやりとしか見えなかったものが、キレイに見えるようになります。ちなみに、写真では、マイクロメータをみています。
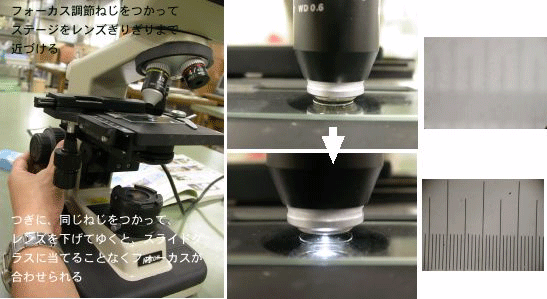
光はレンズで集められています。このレンズの位置がずれると、光がかたよって、視野の中で、暗いところと、明るいところができてしまいます。
そこで! プロは光の軸合わせをします。
光の軸合わせを、芯出し(しんだし)と言います。中心を合わせることです。右の図をみてください。芯出し調節前は上の方が影になっていますが、調節後は、暗いところがありません。
では、芯出し(しんだし)の方法を、下に右の図の番号に合わせてせつめいします。
- まず、「しぼり」をしぼってみます。「しぼり」をしぼると、見えているところが暗くなります。でもよくみると、ほかより明るいところがみえるようになります。これは、光の軸がずれているからです。
- 次に、「コンデンサー高さ調節ねじ」をつかって、コンデンサーを動かしてみます。しぼりにフォーカスをあわせると、しぼりのすがたがみえるようになります。六角形をしたしぼりがみえていますね。
- 今度は、しぼり芯出し調節ねじをつかって、この六角形をまんなかに持ってきます。なかなかむずかしいところです。二つのねじを使って、うまくまんなかにしてください。
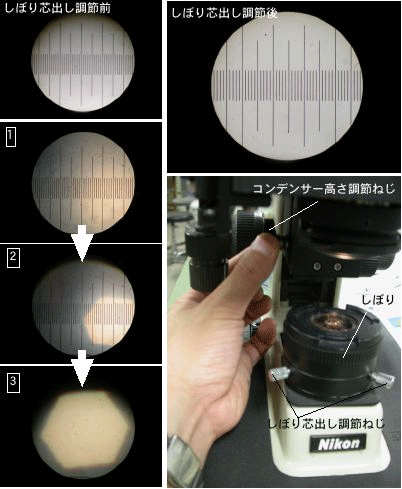
マイクロメーターを使うと、けんびきょうの中に見えているプランクトンなどの大きさをはかることができます。あいては小さいので、小さいもの用のじょうぎをつかうのです。すごいっしょ!
マイクロメーターは、2つしゅるいがあります。
- 接眼マイクロメータ:接眼レンズにはめる。ただし、実際の長さはわからないじょうぎです。
- 対物マイクロメータ:ステージにのせて接眼マイクロメータの1めもりがどれくらいの長さかをはかるじょうぎです。
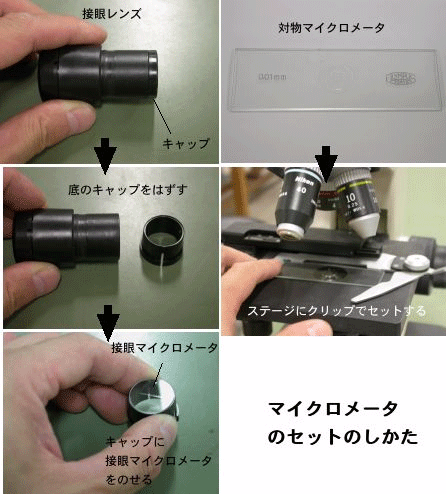
接眼レンズの底のキャップをはずします。そして、そのキャップの上に丸いガラスの接眼マイクロメータをのせて、また接眼レンズにはめるだけ。
対物マイクロメータは、ステージにのせるだけです。
大きなじょうぎの絵が、対物マイクロメータのめもりです。そのまんなかに、小さなじょうぎの絵がみえます。これは、接眼マイクロメータのめもりです。
二つのめもりをよく見てみると、30と70のところで、めもりがかさなっているようにみえます。
このめもりの線がかさなっているあいだのめもりの数をかぞえます。
接眼マイクロメータが40めもり、対物ミクロメータが10めもりとなっています。
ここで、対物ミクロメータの1めもりは、本当のじょうぎで、その長さは、0.01 mm です。
そこで、接眼ミクロメータの1めもりの長さをもとめるためには、右の式をつかいます。答えは、0.0025 mm となります。
これで、接眼ミクロメーターのめもりの長さがわかったら、対物ミクロメータをステージからはずして、測りたいプランクトンの入っているプレパラートを観察すると、プランクトンの長さをしることができます。
どう、すごいっしょ!
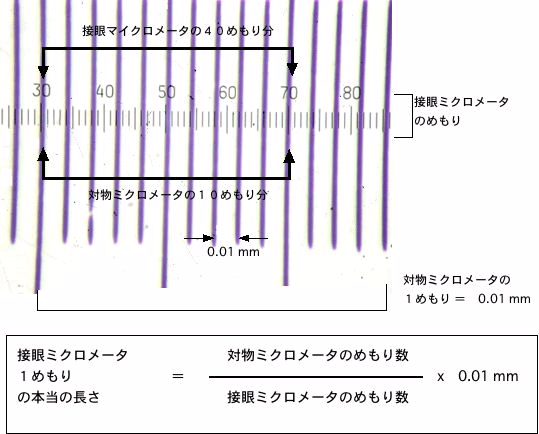
注意!
対物レンズをかえたら、かならず、もう一度はかってください。そうしないと、ほんとの大きさはわからないよ。
レンズの倍率がかわると、接眼レンズでみているサイズもかわります。対物レンズをかえるたびに、この方法をつかって、計算をしてください。そうすれば、正確に長さをはかることができます。