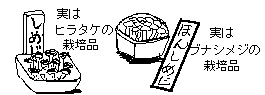 (注1) 「しめじ」と平仮名で記したのは、これが商品名だからです。ふつう「しめじ」といって売られているものはヒラタケの栽培品です。また、「ほんしめじ」といって売られているものはブナシメジの栽培品です。最近はヒラタケやブナシメジと表示されたものも多くなってきているようです。
(注1) 「しめじ」と平仮名で記したのは、これが商品名だからです。ふつう「しめじ」といって売られているものはヒラタケの栽培品です。また、「ほんしめじ」といって売られているものはブナシメジの栽培品です。最近はヒラタケやブナシメジと表示されたものも多くなってきているようです。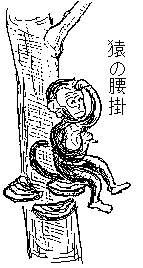 (注2) 「さるのこしかけ」というのは、タコウキン科・マンネンタケ科・タバコウロコタケ科などの菌が作る、樹木の幹などに発生する硬質のキノコに対する総称です。サルノコシカケという種はありません。
(注2) 「さるのこしかけ」というのは、タコウキン科・マンネンタケ科・タバコウロコタケ科などの菌が作る、樹木の幹などに発生する硬質のキノコに対する総称です。サルノコシカケという種はありません。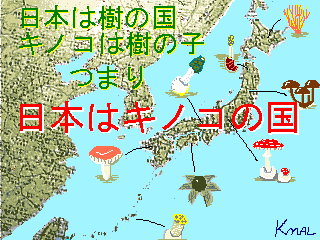 日本は温暖湿潤な気候に恵まれた国で、植物の種類がたいへん豊富な地域です。面積こそ狭いものの日本には樹木だけでも1000種を越える種類が見られます。この数はヨーロッパ全体で見られる樹木の種数に匹敵するそうです。
日本は温暖湿潤な気候に恵まれた国で、植物の種類がたいへん豊富な地域です。面積こそ狭いものの日本には樹木だけでも1000種を越える種類が見られます。この数はヨーロッパ全体で見られる樹木の種数に匹敵するそうです。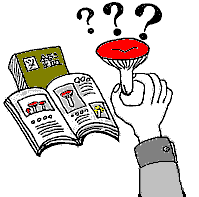 日本にキノコは何種類くらいあると思われますか。この問いには残念ながら正確に答えることができません。研究が遅れており、よく分かっていないからです。
日本にキノコは何種類くらいあると思われますか。この問いには残念ながら正確に答えることができません。研究が遅れており、よく分かっていないからです。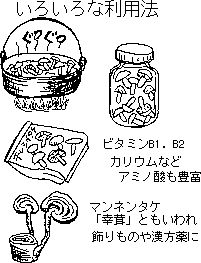 日本人はキノコをよく食べる民族だそうです。
日本人はキノコをよく食べる民族だそうです。
観察会などで「キノコ」と聞いて思いうかべる種類をいってもらったことが何度かあります。
「シイタケ、マツタケ、しめじ(注1)、エノキタケ、ナメコ、マッシュルーム」は必ず出てくる種類です。これらの名があがるのは食用として栽培され、食卓に登場する機会が多いためでしょう。これらのほかに「マイタケ、キクラゲ、さるのこしかけ(注2)、冬虫夏草」などが出てくることもあります。マイタケは、さるのこしかけの仲間です。たまにキクラゲは海に漂っている生き物だと思っている人がいますが、キクラゲはキノコの1種です。さるのこしかけや冬虫夏草は漢方薬としてその制癌作用などが注目を集めています。これらのキノコは食用や薬用として有用なものとして捉えられているようです。
一方、観察会で採集した野生のキノコについて「そのキノコは食用になりますか」とか「毒キノコではないのですか」と聞かれることも多いです。見慣れない野生キノコに対する警戒心が強くあるようにも感じています。
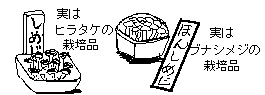 (注1) 「しめじ」と平仮名で記したのは、これが商品名だからです。ふつう「しめじ」といって売られているものはヒラタケの栽培品です。また、「ほんしめじ」といって売られているものはブナシメジの栽培品です。最近はヒラタケやブナシメジと表示されたものも多くなってきているようです。
(注1) 「しめじ」と平仮名で記したのは、これが商品名だからです。ふつう「しめじ」といって売られているものはヒラタケの栽培品です。また、「ほんしめじ」といって売られているものはブナシメジの栽培品です。最近はヒラタケやブナシメジと表示されたものも多くなってきているようです。
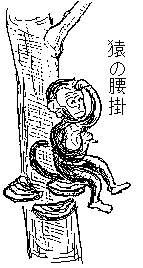 (注2) 「さるのこしかけ」というのは、タコウキン科・マンネンタケ科・タバコウロコタケ科などの菌が作る、樹木の幹などに発生する硬質のキノコに対する総称です。サルノコシカケという種はありません。
(注2) 「さるのこしかけ」というのは、タコウキン科・マンネンタケ科・タバコウロコタケ科などの菌が作る、樹木の幹などに発生する硬質のキノコに対する総称です。サルノコシカケという種はありません。
図のように猿が腰掛けているさるのこしかけを是非1度見てみたいものです。見たことある、写真撮ったよ、という方は是非連絡下さい。