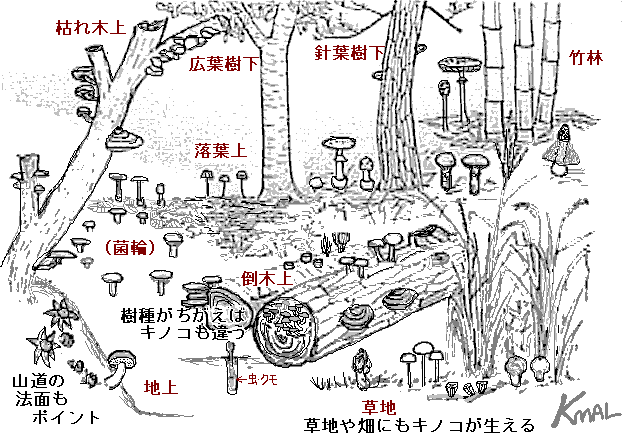
 まず近くの林に行ってみましょう。神社の裏山や公園などドングリのなる木やマツの木が植えてあるような場所がいいです。魚釣りでは川や海に行くのと同じように、キノコ採りでは林に行くのが基本です。キノコの多くは、文字通りの「木の子」であり、樹木や植物のないところにはあまり生えません。
まず近くの林に行ってみましょう。神社の裏山や公園などドングリのなる木やマツの木が植えてあるような場所がいいです。魚釣りでは川や海に行くのと同じように、キノコ採りでは林に行くのが基本です。キノコの多くは、文字通りの「木の子」であり、樹木や植物のないところにはあまり生えません。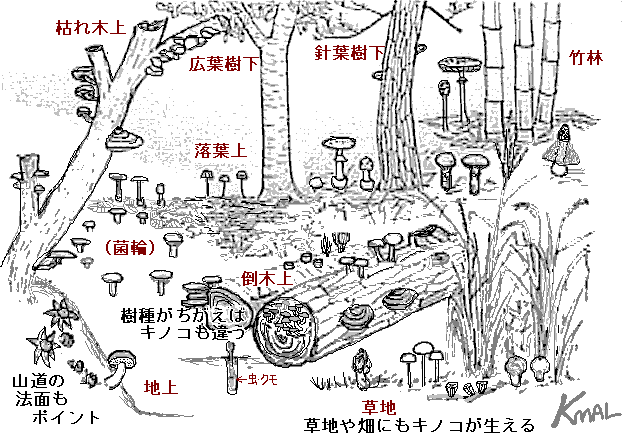
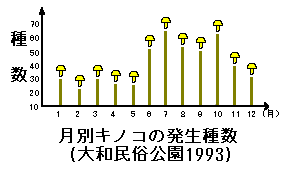 「キノコのシーズンといえば秋」と思われがちですが、種類を問わなければ、キノコは年中見ることができます。しかし、気温と降水量が関係しますので、多くの種類が発生する時期は、平地では6月から7月と9月から11月頃になります(グラフを参照)。この期間でも最高気温が30℃を越え乾燥する日が続くと発生が少なくなるようです。林の状態によっては秋よりも梅雨明け頃にたくさんのキノコを見られることがあります。
「キノコのシーズンといえば秋」と思われがちですが、種類を問わなければ、キノコは年中見ることができます。しかし、気温と降水量が関係しますので、多くの種類が発生する時期は、平地では6月から7月と9月から11月頃になります(グラフを参照)。この期間でも最高気温が30℃を越え乾燥する日が続くと発生が少なくなるようです。林の状態によっては秋よりも梅雨明け頃にたくさんのキノコを見られることがあります。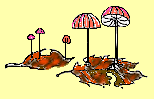 お店で売っている「しめじ」や「エノキタケ」に木のかけらやおがくずがついていることがあります。積み上げられた丸太から生えているシイタケを見たという人もいるでしょう。野生キノコにも倒木や立枯れた幹などに生える種類があります。
お店で売っている「しめじ」や「エノキタケ」に木のかけらやおがくずがついていることがあります。積み上げられた丸太から生えているシイタケを見たという人もいるでしょう。野生キノコにも倒木や立枯れた幹などに生える種類があります。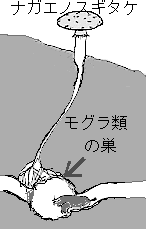
ところが実際に外に出てみると枯れ木以外のいろいろな物からキノコが生えていることに気づくでしょう。落ち葉から生えているように見えるもの、地面から生えているように見えるものがたくさんあるでしょう。そのキノコが地面から生えているのか、腐った落ち葉から生えているのか、埋もれた木材から生えているのか、本当のところはキノコの根元を注意深く掘って確かめるほかありません。もっと変わった物(生きた樹木の根や昆虫の死体やモグラの便所跡など)から生えていることもあります。