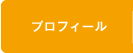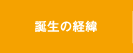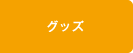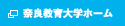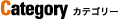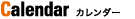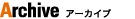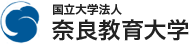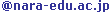平成25年度入学式を挙行しました。
Date2013/04/09
平成25年4月3日、奈良教育大学講堂において、平成25年度入学式を挙行しました。
満開の桜の下、350名の新入生が、緊張した面持ちで奈良教育大学での新たな生活をスタートさせました。
長友恒人学長からは、「大学生活において『学びの習慣化』『協調・協同・仲間作り』『教養、体験の重要性』の3点が特に重要です」「広い視野をもって、大きすぎるくらいの目標を掲げて、みなさんのモラトリアムを、社会人となるための体験を広め、深い学びを楽しむ期間としてください」とエールが送られました。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
教職員一同、みなさんの本学での生活が充実したものになるよう、応援しております。
【新入生】
- 教育学部 274名 (学校教育教員養成課程274名)
- 大学院教育学研究科 65名 (修士課程47名、専門職学位課程18名)
- 特別支援教育特別専攻科 11名


満開の桜の下講堂へ 告辞を述べる長友学長
■ 学長告辞
本年度は、教育学部274名、大学院教育学研究科65名、特別支援教育特別専攻科11名、合計350名の入学生を迎えることができました。本学教職員を代表して、みなさんの入学を心から祝福し、歓迎いたします。
さて、みなさんが本日入学するまでに小学校・中学校・高等学校で受けてきた学校教育は、人類がこれまでに築きあげ、体系化した学問の成果を、小・中・高のそれぞれの段階に応じて理解し、吸収するものでありました。別の言い方をすれば、「既に答えのある問題の解」を理解し、自分の知識としてまとめあげるプロセスでありました。これからの大学での学びは、自らの関心に焦点を当て、課題を発見し、その課題の解決に向けて自ら解答を模索する」という「研究」の要素を含みますから、これまでのように「答えのある問題の解」を理解するだけでは十分ではありません。
みなさんは、「中央教育審議会」という機関をご存じだと思います。中央教育審議会は、文部科学大臣の諮問に応じて「教育」、「生涯学習」、「スポーツ」等について、調査・審議して文部科学大臣に意見を述べる機関です。中央教育審議会の答申は、諮問に対する意見であり、教育に反映されます。
昨年の8月28日に中央教育審議会は、大学の教育および教員の資質能力向上に関して重要な答申をいたしました。
大学教育に関しては、「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて -- 生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ --」という答申です。文部科学大臣の諮問から、4年をかけた審議の結果であります。
教員の資質能力向上に関しては、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」という答申がありました。
この2つの答申は、諮問の背景である社会情勢についての現状認識が共通しています。"大学教育に関する答申"では「予測困難なこれからの時代」という表現で、また、"教員の資質能力向上に関する答申"では「社会の急激な変化に伴って高度化・複雑化する諸課題」という表現で、複雑に変化し、先行きが不透明な社会を認識しています。
現状認識が共通していますから、答申が示した大学教育・教師教育の方向性にも共通点が多くあります。例えば、"大学教育に関する答申"がいう「持続的な学修経験」は、"教員の資質能力向上に関する答申"の「学び続ける教員」という表現に対応します。また、"大学教育に関する答申"の「答えのない問題に解を見出していくための認知能力」と"教員の資質能力向上に関する答申"の「思考力・判断力・表現力等の育成」も同じ発想からの表現です。さらに、「他者に配慮しつつ主体的な思考を伴う協調性」と「多様な人間関係を結んでいく力の育成」も共通性があります。"大学教育に関する答申"がいう「想定外の事態にあたって的確な判断の基盤となる教養、知識、経験」は"教員の資質能力向上に関する答申"の「基礎的・基本的な知識・技能の習得」に支えられるものであります。
先ほど申しましたように、きのうまでみなさんが経験した教育は、「人類がこれまでに築きあげ、体系化した学問の成果を理解し、吸収するもの」でありました。また、「答えのある問題の解を理解し、自分の知識としてまとめるもの」でありました。それは「基礎的・基本的な知識・技能の習得」として非常に重要なことであります。これは大学でも引き続き必要な「学び」の形ではありますが、大学での学びは、先ほど申しましたように「研究」の要素が加わります。中央教育審議会の答申の言葉を借りれば、「大学での学び」は、習得した「基礎的・基本的な知識・技能」を基礎として、「答えのない問題に解を見出していくこと」であり、そのためには、思考力・判断力・表現力を高めていくことが求められます。さらに、想定外の事態にあたって的確な判断をするために、基盤となる教養、知識、経験が必要であります。
ここで、中央教育審議会の答申を踏まえつつ、みなさんがこれから過ごす大学生活において重要なことを3点強調しておきたいと思います。
○まず、「学びの習慣化」です。
自ら学び続けるために、まず、基礎基本の知識や技能が身についているかどうかを自問してください。そのうえで、学ぶ目的が明確であることが必要です。それに加えて、学びが楽しいということを見つけてください。義務的な「勉強しなければいけない」では学びを継続できないし、発展的な考えは浮かびません。「学び」を楽しむために、大学の外にも学びの場を見つけて下さい。興味・関心に従って教室から飛び出して下さい。海外に学びの場を求めることもお薦めします。大学は「学び方を学ぶ場」であります。大学院と特別専攻科のみなさんは、学びの目的はもとより明確であり、既に研究の手法を身につけていると思います。さらに磨きをかけて、もう一段の高みに上っていただきたいと思います。
○2つめに強調したいことは、協調・協同・仲間作りです。
学びには、一人でする学びとチームで行う学びがあります。どちらも必要であり、どちらも有効です。思索が必要なときはひとりで寝食を忘れることもあるかもしれません。グループで行う場合には、何よりもコミュニケーションを密にして自分の役割を意識することがよりよい結果を生みます。コミュニケーションで重要なことは、自己を正確に表現し、他者をありのままに理解することです。そこに、自己の主張をもちつつ、他者の意見も尊重するというグローバル性も養われます。大学生活のなかにおいて、学習や研究環境の中における友人関係だけでなく、課外活動の中での人間関係もチームプレイのための社会性を身につけるいい機会です。課外活動や学校支援活動のなかで、人と人、人と組織、人と地域を繋ぐリーダーシップを自分のものにください。
○3つめは、教養、体験の重要性です。
学びを深めるためには、「裾野」を広げることが必要です。「裾野」を広げるために、大学の授業の他に、課外活動に、フィールドワークに、ボランティアに取り組むことが有効でしょう。自分とは異なる視点からの考え方にヒントを得ることがあるかもしれません。留年覚悟で海外に出たり、留学生と交流することも効果的かもしれません。いろいろな本を乱読してください。学生時代の知的体験、実践的体験が多ければ多いほど、専門についての理解が深まります。このことが、「想定外の事態にあたった時の的確な判断の基盤」となるのです。「答えのない問題に出会ったときに、最善の解を導く源泉」となるのです。大学生活における知的体験、実践的体験は、困難にぶち当たったときに解決の糸口を切り開く潜在的な力になります。それは、また、人生を楽しく、豊かにします。学生時代にどれだけ広く、また深く、いろいろな世界を知り、体験したかということがみなさんの人生を豊かにします。
ここで、私の学生時代の経験をお話しします。3回生の最後の数ヶ月間、私は大学の授業にほとんど出席しませんでした。その理由を格好良く言えば、「人生に悩んだために」ということでありますが、単純に「授業に積極的について行くことができなくなったから」と言ってもいいと思います。私にとっては、この経験が卒業後の人生の大きな糧になりました。授業を欠席した数ヶ月の間に、文学書、哲学書、歴史書を60冊ほど読みました。この数ヶ月は、その後の研究生活、教育者としての生活にとってはよかった、と肯定的に思い出す経験であります。その後の私の大学教員としての生活のなかで、研究と教育の幅を広げ、人との交流に色を添えたという点で、自然科学系の専門書ではなく、様々な分野の本を乱読したこの経験が活かされました。誤解しないでいただきたいのですが・・・「授業を欠席した数ヶ月」がよかったのではなく、「文学書、哲学書、歴史書を読み、思索にふけった数ヶ月」が、結果的にその後の生き方で、柔軟なフレキシブルな思考の一助になったということであります。
みなさんの青春のなかで、答えが浮かばない、解決の方法が見つからないことがしばしばあるかもしれませんが、焦る必要はありません。学生時代に体験した教養、幅広な学習が社会人になった後にも学びを継続してプロフェッショナルな教員・職業人として成長を続けることができるかどうか、人生を豊かにするかどうか、の礎になることを強調しておきたいと思います。
20世紀の心理学者であるアメリカのエリクソンは、「人が成長して、なおかつ社会的義務が猶予される期間」をモラトリアムといいました。学生時代は、「社会人ではない大人の時期」あるいは「社会人になるための準備期間」という意味でモラトリアムであります。広い視野をもって、大きすぎるくらいの目標を掲げて、みなさんのモラトリアムを、社会人となるための体験を広め、深い学びを楽しむ期間としてください。
みなさんの本学での生活が、豊かで、充実した未来に繋がるものになることを希望して、告辞といたします。
平成25年4月3日 奈良教育大学長 長友 恒人
音楽教育講座 福井一教授 カネボウ化粧品との共同研究成果を発表しました。
Date2013/04/05
音楽教育講座 福井一教授 と 株式会社カネボウ化粧品 が共同研究を行い、幻の香り素材として知られる「龍涎香(りゅうぜんこう)」に含まれる主要香気成分のひとつであるテトラノルラブダン オキサイドについて、ストレスを軽減させるリラックス効果が期待できること、また、その香りをつけている人物の表情が他人から見て"親しみやすい"印象と評価される傾向があることを確認しました。
詳細は、株式会社カネボウ化粧品提供のプレスリリース記事をご覧ください。


福井 一 教授 龍涎香(提供:国立科学博物館)
※ 広報誌「ならやま」2011年春号で、福井教授の研究を紹介しています。
https://www.nara-edu.ac.jp/guide/bulletin/narayama/#move_660
平成24年度卒業・修了式を挙行しました。
Date2013/04/01
平成25年3月25日、奈良教育大学講堂において、平成24年度卒業式及び修了式を挙行しました。
桜はわずかに咲き始めた程度でしたが、スーツ姿やあでやかな着物姿の卒業生たちの笑顔が、会場を彩っていました。
長友恒人学長からは、「『振り返り』により、『学びと体験』は単なる経験の蓄積から体系化されたものになり、自らの向上につながる。楽しみながら学びを継続してもらいたい」「自分とは異なる考えをもつ他者がいることを理解し、その他者と一緒に働く方法を知ることで協同が可能になり、コーディネーターとしてのリーダーになることを可能とする。みなさんには、リーダーシップを発揮することを期待する」とエールが送られました。
卒業生、修了生の皆さん、おめでとうございます。
本学で得られたものを生かしご活躍されることを、心よりお祈りいたします。
【卒業・修了生】
- 教育学部 256名 (学校教育教員養成課程180名、総合教育課程76名)
- 大学院教育学研究科 74名 (修士課程57名、専門職学位課程17名)
- 特別支援教育特別専攻科 11名


告辞を述べる長友学長 音楽科学生による生演奏での学歌斉唱
■ 学長告辞
ただいま、教育学部256名、大学院教育学研究科74名、特別支援教育特別専攻科11名、合計341名に卒業証書、修了証書を授与いたしました。
卒業生、修了生のみなさん、おめでとうございます。大学教職員を代表して皆さんの卒業・修了を心から祝福いたします。また、ご列席の保護者の皆様におかれましても、ご子弟の晴れ姿に感慨もひとしおのことと、心からお慶び申し上げます。
学部を卒業するみなさんが入学した4年前の2009年(平成21年)はどういう年であったでしょうか。4月5日、入学式の前日に北朝鮮が弾道ミサイル開発とみられるテポドンを発射しました。そして、みなさんが4回生になって、卒業論文の最終盤にかかった昨年12月には、初歩的な衛星ではありますが、人工衛星を軌道に乗せることに成功しました。もちろん、私は「卒業式」のはなむけの言葉として、ここで、「北朝鮮のロケット開発」のお話をしようというわけではありません。社会の中の一員としての自己を、歴史の中に置いて見つめていただきたい、という主旨であります。
そういう点から、みなさんが本学で過ごしたこの期間を振り返れば、経済的には沈滞の季節であり、文化等の領域でも世の中に躍動感はありませんでした。また、2年前の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故は、防災への反省と対策だけではなく、私たちの生活全般の在り方についても再考を促すものでありました。このように見ると、沈滞した、躍動感のない、表面的にはつまらない社会情勢の時代に貴重な青春時代を大学で過ごしたかのように見えます。
しかし、いつの世も、沈滞しているときは「次の飛躍」に向かって、底流が活発に動いている時でもあります。きょう卒業・修了するみなさんは、意識するとしないに関わらず、高等教育機関、とりわけ教員養成に関わる高等教育行政の歴史の大きなうねりの中で、本学で学びの期間を過ごしました。さきほどは「社会の中の一員としての自己」と申しましたが、大学もまた、社会から独立しては存在できません。大学の外から、とりわけ経済界からの、大学をはじめとする高等教育機関に対する批判や要求には厳しいものがあります。その背景には、経済の沈滞があります。景気がよかった時期には、「とにかく、大卒者を採用したい。現場で役に立つ教育は企業がします。」という状況でしたが、企業内教育の余裕がなくなった現在は、「即戦力になる人材を求める。」という状況になっています。教育界でも、背景は異なりますが、「即戦力になる人材」が求められているという点では同様です。
大学は社会から独立した存在ではなく、国民の負託を受けて、存在しているのですから、経済界のみならず、社会の意見に耳を傾けるのは当然のことですが、ここで、「不易と流行」という松尾芭蕉の言葉を想起することが重要でしょう。「不易と流行」は色々な場面で使われる言葉でありますが、特に、今、教育において変えてはならない「不易」は何か、変えるべき「流行」は何かを意識することが非常に重要であると考えます。
「流行」の部分に相当する発言が多い中で、経済界からも識者の発言として、グローバル人材に必要なものとして、「コミュニケーション能力、ネゴシエーション能力や語学力」と並んで、教養教育が強調されていることに注目したいと思います。大学設置基準の大綱化により、科目区分規定としての一般教育科目・専門教育科目の垣根が取り払われ、削除されたのが1991年のことでありますから、それから20年を経て、改めて教養教育の重要性が表立って議論されるようになりました。三村明夫中央教育審議会会長は新日鐵住金株式会社の取締役相談役でもありますが、「海外で業務を遂行できるグローバル人材を育てるために教養教育の確立が課題である」と発言されました。また、別の経済人は「相手を理解し、相手の立場に立って考えるためには歴史や哲学から学ぶ事が必要であり、その意味で「リベラルアーツ」が重要である、という趣旨の発言をされています。
教養教育は、大学をはじめとする高等教育で基本的に重視すべき「不易」のひとつであります。学校の教員になるにしろ、公務員や企業で働くにしろ、「教養」は社会で生きる人の基本として身につけるべきものであります。「身につけるもの」というよりは、「身につくもの」という方が教養の性格を示すのに相応しいだろうと思います。大学の限られた授業時間で修得できなかった学びは、社会人となって働き、人と接する中で継続して深められますが、その継続した学びを確実なものにするのが「教養」であります。
昨年8月に中央教育審議会から2つの重要な答申が出されたことはご存じと思います。「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」と「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」であります。2つの答申に共通していることは、「生涯を通じて学び続け、主体的に考え、資質能力の向上を図ること」であります。これを可能にするためには、ハウツーものは何の役にも立ちません。教養をベースにした学びを継続することが必要です。この2つ、「教養を身につけること」と「学びを継続すること」には共通点があります。どちらも、他者から押しつけられて勉強するものではなく、自らの、主体的な行為として、無意識に学ぶ、という点です。意識して「教養」のために勉強するのではなく、学びと体験を継続し、振り返ることによって、教養は豊かになり、資質能力が向上することになります。大事な事は「振り返る」ことであります。「振り返り」によって、「学びと体験」は単なる経験の蓄積から体系化されたものになり、自らがスパイラルに向上することに繋がります。学びを継続するコツは、学ぶことが楽しいということです。明日からの生活の中でも、楽しみながら学びを継続していただきたいと思います。
もうひとつ、みなさんがこれからの社会生活の中で意識していただきたいことがあります。
外国が日本の教育からくみ取るべきものとして、「教育が国の将来にとって重要であるという信念を(国民が)共有していること」、「素質よりも努力を重視する」、「教員による授業研究が専門的力量、質の高い授業を保証している」、特に「モラル教育」は社会生活の多くの場面、例えば、商業における倫理感や持続可能な環境の維持、にまで大きな影響を与えていること、等が指摘されます。私たち日本人にとっては当たり前のことであって、言われてみればそうですね、ということかと思いますが、逆に、私たちに欠けていること、あるいは外国に見習うべきことを挙げるとすれば、そのひとつが「リーダーシップ」であります。
今、学校でも、企業でも、地域社会でも必要とされるのはリーダーの存在です。リーダーという言葉は他者の牽引役となり、指導できる人という意味で使われることがありますが、学校や社会が必要としているリーダーは、そういう意味でのリーダーではありません。専門的な知識を持って、人と人(学校で言えば、同僚である教師と教師、教師と保護者)を、人と組織(学校と教育委員会)を、人と地域(学校と地域)を繋ぎ、コーディネートする役割を果たす人、これが今必要とされているリーダーです。
自分とは異なる考えをもつ他者がいることを理解し、その他者と一緒に働く方法を知ることが共に働くこと、協同することを可能にし、人と人、人と組織を繋ぐコーディネーターとしてのリーダーになることを可能にします。
みなさんには、明日からの教師として、あるいは社会人としての生活の中で、リーダーシップを発揮することを期待します。
学びは生涯を通じて継続されるものです。みなさんが、明日からも、幅広く知識を吸収し、学びを継続することによって、学びを楽しみ、続けることによって、諸君の輝く未来が開かれることを信じて、告辞といたします。
平成25年3月25日 奈良教育大学長 長友 恒人