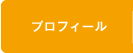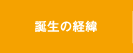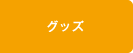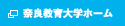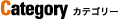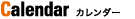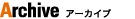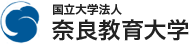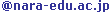附属幼稚園入園式でなっきょんがお見送り!
Date2012/04/16
平成24年4月13日、満開の桜のもと附属幼稚園で入園式が挙行されました。
当日はなっきょんが幼稚園正門付近に登場、入園式を終えた新入園児達を見送りました。突然のなっきょんの登場に、園児達は大喜び。保護者の方を含めて写真撮影の行列ができました。特に附属幼稚園の制服(スモック)を着たなっきょんの登場とあって、より親近感を持っていただけたでしょうか?
これからの新しい生活、なっきょんはいつでも皆さんを見守っています!


平成24年度入学式を挙行しました。
Date2012/04/06

 入学式会場の様子 クラブの勧誘を受ける新入生
入学式会場の様子 クラブの勧誘を受ける新入生本日、ここに、ご来賓として、赤井元学長、大久保元学長、柳澤前学長先生をはじめ、名誉教授の先生がた、同窓会の会長・副会長様のご列席の下、平成24年度の入学式を挙行できますことは、本学教職員の大きな喜びであります。
本年度は、教育学部274名、大学院教育学研究科92名、特別支援教育特別専攻科10名、合計376名の入学生を迎えることができました。本学教職員を代表して、みなさんの入学を心から祝福し、歓迎いたしますとともに、みなさんの学びと研究に対する指導・助言、大学生活に関する相談と援助について最大限の努力を惜しまないことをお約束いたします。
さて、ご承知の通り、今年度から教育学部の入学定員255名をすべて学校教育教員養成課程といたしました。学校教員の需給の状況から判断してのことでもありますが、教育理論の理解、教科の専門的力量の強化に加えて実践的な教育力を身につけたプロフェッショナルな教師として教育界に送り出すことを全学的な目標としたいということであります。大学院教育学研究科、特別支援教育特別専攻科に入学されたみなさんを含めて、これから教員となる人たちは、21世紀の日本と世界を担う子ども達を育成する高度な専門性を備えた教育者としての力量が求められます。
学部入学のみなさんは、小学校から高等学校まで12年間の教育を受けてきました。この12年間の学びと大学での学びはどう違うのでしょうか。高校までの学びは、これまで人類が築いてきた歴史の成果、とりわけ学問の成果を吸収し、自分のものとして組み立て直すことが主な目標でありました。大学での学びは、「自らの関心に焦点を当て、課題を発見し、その課題の解決に向けて自ら解答を模索する」という研究の要素が加わります。大学での学びの目標は、教室で先生から教えてもらうだけで到達できるものではありません。高校までの学びを「学び習う」学習と書き、大学での学びを「学び修める」学修と書く所以であります。興味・関心に従って教室から飛び出して下さい。極めるために、大学の外にも学びの場を見つけて下さい。海外に学びの場を求めるのも大いにお薦めしたいことです。
大学院と特別専攻科のみなさんは、既に研究の手法を身につけていると思います。さらに磨きをかけて、もう一段の高みに上っていただきたいと思います。
ここで、最近の私の「学びの体験」をお話ししたいと思います。
2006年から今年の3月まで6年間、「環境変化とインダス文明」という総合地球環境学研究所の大型プロジェクトに参加させてもらいました。 このプロジェクトは、“現在のパキスタン領にあるインダス川流域のハラッパー遺跡やモヘンジョ=ダーロ遺跡に代表されるインダス文明は世界四大文明の一つとして知られていますが、インダス川流域だけではなく、インド西部のガッガル川沿いやグジャラート州など、日本列島の約2倍にあたる68万平方キロにわたってインダス文明の遺跡がひろく分布しています。インダス文明は、他の古代文明と異なり、紀元前2600年から約700年間しか続かず、紀元前1900年頃に急速に衰退しました。環境変化を中心にインダス文明が短期間で衰退した原因を解明し、長期的な環境変化が文明に及ぼす影響をあきらかにすることによって、現代の環境問題の解決に資すること”を目的とした研究でありました。
ガッカル川流域の現地調査を含めて年代測定研究者として参加したこの研究プロジェクトから学んだことがいくつかあります。
ひとつは・・・このプロジェクトは6つの研究グループで構成されています。考古学を中心とする物質文化、農業生産を再現する生業、現在に繋がる伝統文化、過去の水環境を探る古環境、そして遺伝学の6つでありますが、プロジェクトリーダーの長田俊樹教授のご専門は民族言語学です。言語学者がインダス文明の衰退を解明しようとしたとき、自分の学問領域に固執することなく、広く考古学・植物学・民俗学・地形学・遺伝学などの分野にも視野を広げたという総合的・学際的な発想がプロジェクトの成功を保証しました。専門領域を深く解明しようとするとき、自分の領域に閉じこもるのではなく、他の関連領域と協同することによって新しい展開があるという好例でありました。
もうひとつは、楽しみながら学ぼうとする姿勢です。遺伝学の研究グループはプロジェクトの終了期限までに結果を出すことができなかったのですが、最終報告会で最も活発に質問をしたのは遺伝学のコアリーダーでした。コアリーダーはDNA解析結果を出すことができなくても、プロジェクトのトータルな目的が達成されることに多大の関心をお持ちのように見えました。彼の質問は研究会を活気づけてくれたのです。
また、このプロジェクトの成功は、人生の楽しいことやうれしいことのみを記憶するという楽天的なプロジェクトリーダーの下で、チームとしてのコミュニケーションが円滑であったことにひとつの要因がもとめられるであろう、と思います。日常的なコミュニケーション、定期的な意見交換はひとつの目的に向かって協同して取り組むときの不可欠な要素であります。
自ら学び続けるためには、学ぶ目的が明確であることが必要です。それに加えて、楽しいということが必要です。義務的な「ねばならない」では継続できないし、発展的な考えは浮かびません。学ぶ目的を見極めるためには、自分がやろうとしていることの位置づけを考えることが重要です。例えば、教師になろうとする場合に、教育全般の中でどのような特徴ある専門性を自分のものにするのか、ということを考えることは目標設定の有効な方法になるでしょう。
その学びを深めるためには、「裾野」を広げることが必要です。学びを深める方法はひとつだけではありません。大学の授業の他に、課外活動に、フィールドワークに、ボランティアに、取り組んでください。自分とは異なる視点からの考え方にヒントがあるかもしれません。課題によっては、海外に出たり、留学生とディスカッションすることも効果的かもしれません。いろんな本を乱読してください。学生時代の知的体験、実践的体験が多ければ多いほど、専門についての理解が深まります。
学びには一人でする学びとチームで行う学びがあり、どちらも必要であり有効です。思索が必要なときはひとりで寝食を忘れることもあるかもしれません。グループで行う場合には、何よりもコミュニケーションを密にして自分の役割を意識することがよりよい結果を生みます。学習・研究環境の中における友人関係の他、課外活動の中での人間関係もチームプレイのための社会性を身につける良い機会です。
答えが浮かばない、解決の方法が見つからないことがしばしばあるかもしれませんが、焦る必要はありません。自分で答えが出せないときに、友人、先輩、先生が解決のきっかけを与えてくれるかもしれません。難しい課題に立ち向かうときに重要なのは考えるプロセスです。答えのない問題もあるのだということを理解しておくことも必要かと思います。
大学における知的体験、実践的体験は困難にぶち当たったとき、解決の糸口を切りひらく潜在的な力になります。それは、また、人生を楽しく、豊かにします。
学生時代にどれだけ広く、また深く、いろいろな世界を知り、体験したかということが、社会人になった後にも学びを継続してプロの職業人として成長を続けることができるかどうか、人生を豊かにするかどうか、の礎になることを強調しておきたいと思います。
広い視野をもって、大きすぎるくらいの目標を掲げて、楽しく学び、体験を広めてください。
みなさんの奈良教育大学での生活が、豊かで、充実したものになることを希望して、告辞といたします。


平成23年度卒業・修了式を挙行しました。
Date2012/04/01
平成24年3月23日、奈良教育大学講堂において、平成23年度卒業式及び修了式を挙行しました。小雨が降る、少し肌寒い日となりましたが、真新しいスーツ姿、あでやかな着物姿の卒業生たちが、まだ少しつぼみの固い桜に代わって、華やかに会場を演出していました。
式では、学歌斉唱の後、教育学部卒業生275名の総代として米谷葵さん、大学院教育学研究科修了生66名の総代として東畠代次郎さん、特別支援教育特別専攻科修了生9名の総代として小山悦子さんに長友恒人学長からそれぞれ卒業証書・学位記、修了証書が授与されました。
続いて、学長告辞で、「生涯にわたって学ぶ意欲を持ち、他者と一緒に働く方法を知り、自分とは異なる考え方があることを理解し、間違えを正すことを恐れず、社会への参加意識を高めることを心に刻んでほしい」と社会の一員として巣立つ卒業生らにエールが贈られました。
在学生総代として学生自治会執行委員長 檜垣勇佑さんが送辞で先輩たちへの感謝を述べた後、卒業生及び修了生総代として川合彩香さん(教育学部)から、人との出会いがかけがえのないものとなって成長できたこと、教育実習やスクールサポート活動を通じて、子どもたちから“先生”と笑顔で呼ばれたことが“夢”を後押ししてくれたことが想い出として語られ、最後に「この先訪れる出会いを大切に、幅広く社会に貢献していきたい」と決意が述べられました。
卒業・修了生の皆さん、おめでとうございます!
本学で得られた宝物を大切に、ご活躍されることを心よりお祈りいたします。 

学長告辞を聴く卒業・修了生たち 音楽科学生の伴奏・合唱と共に学歌斉唱
本日、ここに、赤井逹達郎元学長先生、大久保哲夫元学長先生、西田同窓会長様、神木後援会会長様をはじめ、多くのご来賓の皆様にご臨席いただき、平成23年度卒業証書・学位記及び修了証書授与式を挙行できますことは、本学教職員にとりまして大きな喜びであります。
ただいま、教育学部275名、大学院教育学研究科66名、特別支援教育特別専攻科9名、合計350名に卒業証書、修了証書を授与いたしました。
卒業生、修了生のみなさん、おめでとうございます。大学教職員を代表してみなさんの卒業・修了を心から祝福いたします。また、ご列席の保護者の皆様におかれましても、ご子弟の晴れ姿に感慨もひとしおのことと、心からお慶び申し上げます。
さて、現在、産業・経済を軸とする生活は複雑化し、混迷を深めているように見えます。この状況を、「科学技術から経営、社会システムに至るまでパラダイムの転換をもたらすブレークスルーを模索しなければならない厳しい環境」と表現したのは、中央教育審議会大学分科会の「大学教育部会」が今月とりまとめた審議のまとめ、「学士課程教育の質的転換の確立」であります。
ブレークスルーを模索しなければならないのは、科学技術や産業・経済だけではなく、教育の面においても、同様であります。
OECDが2000年から実施している学習到達度に関するPISA(Program for International Student Assessment)調査をご存じのこと思います。PISAの分析報告として、「PISAから見る、できる国・頑張る国 ---トップを目指す教育」という報告書が昨年の6月に出版されました。英語の原題を忠実に訳しますと、「教育におけるトップクラスの国と改善が著しい国:合衆国がPISAからの学ぶこと(Lessons from PISA for the United States)」というアメリカ向けの報告であります。最近、同書の「Lessons from PISA for Japan」という日本向け報告書の日本語訳も出版されました。いずれもOECDのHPから英語版をダウンロードすることができますので、一読をお薦めします。
Lessons from PISA for the United Statesには、アメリカの他、カナダ・オンタリオ州、上海、香港、フィンランド、日本、シンガポール、ブラジル、ドイツ、イギリス、ポーランドが取り上げられ、附章として韓国が取り上げられています。
同書によりますと、シンガポールは、「考える学校、学ぶ国家 (Thinking Schools, Learning Nation) 」という教育ビジョンを持っています。「考える学校(Thinking Schools)」とは、若者の創造的思考力を伸ばし、生涯にわたって学ぶ意欲を持ち、国への参加意識を高めることができる学校システムのことである。」と説明されています。
フィンランドは人口約540万人で、日本より少し小さい国土がスウェーデンとロシアに挟まれており、苦難の歴史を歩んだ国でありますが、PISAでトップクラスの成績を維持し続けている国であることは周知の通りです。携帯電話端末で世界一のシェアをもつ電気通信機器メーカー、ノキアの経営幹部でもあるサールベリ氏が、フィンランド国家科学カリキュラム対策委員会の委員長を務めていた時期の発言に次のものがあります。企業が、「他人と一緒に働く方法を知らない者、異なる考え方ができない者、独自のアイデアを生み出せない者、そして間違いを犯すことを恐れる者、こういう人を企業が雇った場合、企業ができることは何もない。」というものです。
この報告書の日本に関する章では、合衆国が日本から学ぶべきこととして12項目が挙げられています。その中で、日本は「教育が国の将来にとって重要であるという信念を(国民が)共有していること」、「遺伝的に受け継がれた能力より努力を重視する」、「教員による授業研究が専門的力量、質の高い授業を保証している」、「生きるための道徳教育」が含まれています。ここで、「道徳」は原文ではモラルです。私たち日本人の儒教的感覚の「道徳(モラル)」とは少しニュアンスが違って、勤勉さと粘り強さ、チャレンジすること、奉仕の行為、他者を助けること、謙虚さ、等を指していますが、そのようなことが、日本から学ぶべき教訓として挙げられています。「モラル教育」は社会生活の多くの場面、例えば、商業における倫理感、健康管理、持続可能な環境にまで大きな影響を与えている、と指摘しています。東日本大震災の発生直後に被災者が秩序ある行動を取ったことに対する諸外国からの反応を重ね合わせて考えるとき、日本の教育に関する特筆すべき特徴として取り上げられていることに改めて注目する必要があります。
以上、ごく一部を紹介しましたが、PISAのトップクラスの国々から合衆国が学ぶべき教訓として、共通して強調されていることは、「生涯にわたって学ぶ意欲を持ち、他者と一緒に働く方法を知り、自分とは異なる考え方があることを理解し、間違いを犯すことを恐れず、社会への参加意識を高めること」とまとめることができるでしょう。
このことは、今日、卒業・終了して社会の一員として旅立つみなさんに、心に刻んでいただきたい言葉です。「生涯にわたって学ぶ意欲を持ち、他者と一緒に働く方法を知り、自分とは異なる考え方があることを理解し、間違いを犯すことを恐れず、社会への参加意識を高めること」を大学・大学院での学びの延長の基本としてください。
「21世紀は知識基盤社会である」と言われますが、教師として、あるいは社会人として、「専門知識とスキル」は、他者と一緒に働く方法を知り、自分とは異なる考え方があることを理解して、「他者の専門知識とスキル」と有機的に関連づけたときに大きな力を発揮します。スペシャリストは自分とは異なる分野のスペシャリストを理解したときに初めて、「知識基盤社会」において有能なスペシャリストとして、力を発揮することができます。ふたつのスペシャリティを橋渡しするものは「教養」であり、ひとつのスペシャリティをもつあなた方一人ひとりと他のスペシャリストを結びつけるものは「人としての豊かさ」であろうと思います。精神的な、また、知的な「人の豊かさ」を保証するものは、学び続けることによって獲得することができる「教養」であります。専門知識とスキルに加えて、豊かな「教養」を自分のものにしたとき、プロフェッショナルな高度な職業人となることができるでしょう。
学びは生涯を通じて継続されるものです。みなさんが、明日からも、幅広く知識を吸収し、また、体験する「学び」を継続することによって、21世紀を担うプロフェッショナルな社会人となることを期待します。
みなさんの未来が、輝く未来であることを確信して、告辞といたします。