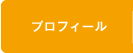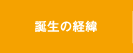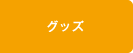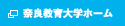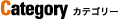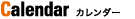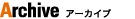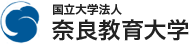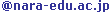「教育支援人材」育成事業の取り組みに関する報告会を開催しました。
Date2012/03/28
本学では、平成24年3月26日に、「教育支援人材」育成事業の取り組みに関する報告会を開催しました。
第一部では、スクールサポート研修・認証制度の概要説明とサポーターとして活動した学生による報告が行われました。同制度は、学校及び地域の教育支援活動に参加する「人材育成」を目的に、平成22年度から実施されており、学校教育活動や子どもの人権・発達等に関する理解を深めた上で活動する研修と、実際の活動の中で学んだ事柄を理論的・反省的に理解し直す研修を修了することで、スクールサポーターとして認定しています。学生からは、「教育実習だけでは得られない貴重な経験ができた」など報告がありました。
第二部では、日本教育大学協会からの研究助成「異世代合同型の研修と連携型育成モデルの構築」を受けて進められた「東市日本一プロジェクト」について、活動した学生や地域住民から報告がありました。同プロジェクトは、奈良市立東市小学校とその校区の地域住民、奈良教育大学学生が同小学校を日本一にしようと取り組む異世代連携型学校教育支援プロジェクトで、平成23年度から実施されており、通学合宿や放課後子ども教室の企画運営などを行っています。参加した地域住民からは、「意欲的な学生の取り組みに感心している」など感想が述べられました。
両事業とも学校や地域から好評を得ており、今後も引き続き実施される予定です。


スクールサポートについて報告する学生 報告に聞き入る参加者
人権・シティズンシップ教育に関する研究フォーラムを開催しました。
Date2012/03/16
本学では、平成24年3月14日に、「二十一世紀の教育にとって何が大切なのか~人権・市民性教育の視点から」をテーマに、人権・シティズンシップ教育に関する研究フォーラムを開催しました。
フォーラムでは、生田周二 持続発展・文化遺産教育研究センター長(当時)、立石麻衣子 奈良教育大学特任講師、藤田和義 奈良県教育委員会人権・社会教育課課長補佐、ロルフ・ゴロップ チューリヒ教育大学教授より、日本・奈良県・欧州における人権教育について報告があり、日本の人権教育ならびに子どもの権利に関わる歴史と状況を踏まえつつ、奈良県の人権教育および欧州評議会の人権教育・市民性教育の動向に学びながら、民主主義社会における人権尊重の方向性、参加や責任のあり方について考え合い、二十一世紀の教育にとって何が重要なのかについて、人権・市民性教育の視点から検討されました。
参加者からは、「厳しい日常があるからこそ、学校では全員で民主主義に基づく社会を築いていこうという共通理解のもと、人権教育に取り組んでいくことが大切だと気付いた」「学校からの発信が、社会を変えられることもあることがわかった。大きな力をいただいた」という声が寄せられるなど、有意義なフォーラムとなりました。


ホワイトボードを使って説明するゴロップ教授 熱心に聞き入る参加者たち
附属小学校教諭による退職記念公開ゼミを開催
Date2012/03/12
本学自然環境教育センターでは、平成24年3月9日に、三上周治同附属小学校教諭を講師として、「教職37年 私が出会った困った(=素敵な)子どもたち」をテーマに公開ゼミを開催しました。
三上教諭は、国公私立の小・中・高校での幅広い教職経験や「学級崩壊」と言われるクラスをいくつも立て直してきた経験を持ち、著書も多数。当日は、実際の経験に基づく貴重な講演を聞くことができるとあって、学内外から70名を超える参加者がありました。
講演では、37年の教職生活を振り返り、実際に出会った子ども達や学級崩壊のクラスを立て直した際のエピソードが披露され、「困った子」と言われる子ども達をよく見ると、「困った」ことを起こさせる要因が外側にあることの方が多かったということや、困った子は実は素晴らしい子ども達であったことなどが明らかにされました。参加者を引きつける軽快な口調でありながらも、学級経営の参考となる実践的な話に、参加者は熱心に聴き入っていました。


三上教諭の講演に聴き入る参加者 講演する三上教諭