- 本学で学びたい方へ
- 在学生の方へ
- 卒業生・修了生の方、現職教員の方へ
- 自治体・企業の方へ
- 一般・地域の方へ
- 教職員の方へ
- 大学紹介
- 入試情報
- 学部・大学院
- 進路・就職
- 教育・学生生活
- 国際交流・留学
- 産官学連携

PDF版「研究者インタビュー」はこちら
いつか死ぬことはわかっているのに、私たちはなぜ生きるのだろう。とくにきっかけはないのですが、昔からぼんやりと人間の生と死、そんなことを考えている人間でした。
この10年ほど、年ごとにばらつきはありますが、日本の自殺者数は減少傾向にあります。でも、10代においてはその傾向が見られません。むしろ、2024年の10代の自殺者数は過去最多となってしまいました。
どうして子どもたちは死を選んでしまうのだろう。それぞれに固有の要因があるのは承知のうえで、心の動きをメカニズムとして理解できれば、止められるかもしれない。道のりは遠く険しいですが、研究の発展の一端に寄与すべく、先行研究とデータに向きあっています。
予防につながる足がかりとして、自殺を考えてしまう心の状態「自殺念慮」を予測する研究を進めています。(▶︎関連論文) 自殺念慮については、精神医学や心理学などの分野でたくさんの研究がなされていますが、最有力とされる理論は約20年前のもの。20年で社会は大きく変化しましたし、それにともなって子どもたちをとりまく状況も変わっています。先行研究をいかしつつ、現在の状況を織り込んで理論を発展できれば、自殺念慮の予測の精度を高められるかもしれません。
自殺の問題と並行して、気分が落ち込み、憂鬱な気分がつづく「抑うつ状態」など、さまざまな要因と関わる「社会経済的地位」についての研究も進めています。
社会経済的地位とは、収入や就学年数、職業などに基づいて、社会のなかでの個人または世帯の位置を示すものです。裕福な人に比べて、貧困状態にある人は精神的に不健康になりやすいのは想像できるかもしれません。社会経済的地位の低さは、「やればできる」という意欲を奪うのです。先行研究では、世帯の社会経済的地位の低さは、その世帯の子どもの成績や抑うつ傾向にも大きな関連があると示しています。その一方で、日本の学校は、子どもたちの家庭の社会経済的地位の測定に後ろ向きです。そこで、そうした後ろ向きな気持ちを生じさせずに、社会経済的地位を間接的に測定する方法を開発しました。(▶︎関連論文)
さらに、この社会経済的地位と抑うつとの関係は、「金融リテラシー」によって変わるのではないかと考えました。金融リテラシーは、お金や経済、金融に関する情報を正しく理解して、自分で判断できる力のことです。
日本で働く2,173人にアンケート調査を実施して、金融リテラシーの高い人は低い人に比べて、社会経済的地位と抑うつとの関係が弱まる結果を示すことができました(図)。つまり、社会経済的地位が低くとも、金融リテラシーが高ければ、抑うつ傾向を抑えられることを示唆しています。
家庭の社会経済的地位をすぐに変化させることはむずかしいですが、金融リテラシーならば教育しだいで向上させられる。すると、「なにもできない」と思っていた人たちが、「なにかできそうだ」と将来の展望を前向きに捉えられるかもしれません。貧困にともなう抑うつ状態の緩和や、ひいては貧困問題の解決の糸口になればと期待しています。
研究手法の主たる部分は、アンケート調査と、そのデータをもちいた統計解析。アンケート調査をとおして〈いま、対象者が感じていることや考えていること〉にふれると、回答者の顔は見えなくとも、一人ひとりの存在を感じます。身近な問題に取り組んでいるという実感がわき、やりがいにつながっています。
調査の実施前には、いろいろな可能性を考えに考え抜いて、「こうなるはずだ」と仮説を立てて実行しますが、思ってもみない結果は当然のように起こります。そこで投げ出さず、「仮説となにが違うのか」をぐっと深く考える。諦めず腐らずに向きあえば、理論はかならず発展すると信じています。
研究をつづけたさきにめざすのは、どの時代の人間にも当てはまるような普遍的な心理メカニズムの解明。着目する事象はそのときどきで変わっても、いつか人間の本質にたどり着けるように歩みを進めたいです。
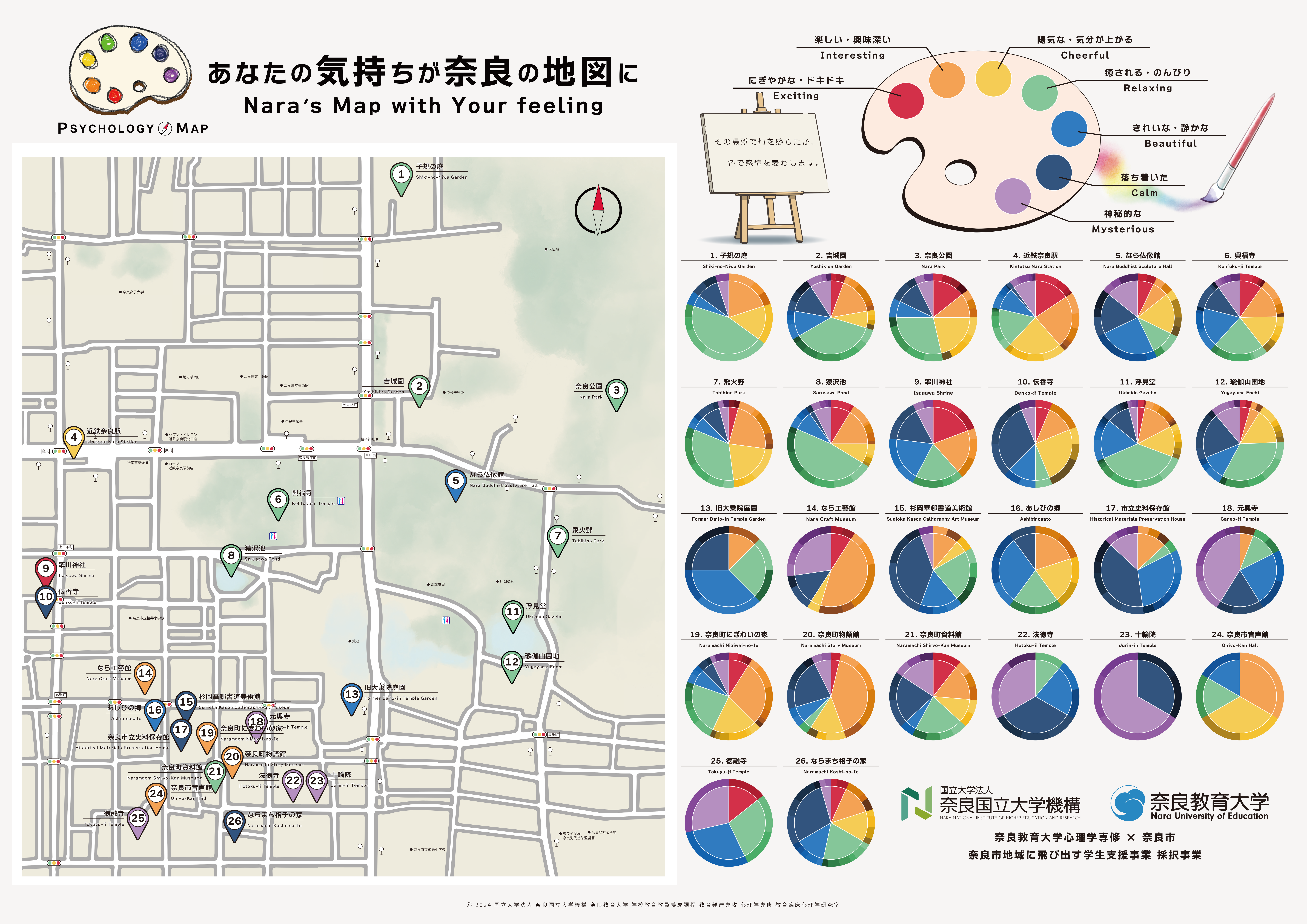
心理学専修の授業で、学生たちが主体となって、心理学の知見に基づいた奈良の観光マップをつくりました。観光スポットを訪れたときに感じた気持ちを色で表現したものです。奈良公園など、26か所でアンケート調査を実施。「どんな気持ちになりたいか」から訪ねる観光地を決められます。奈良交通がレンタサイクルの利用者向けに配布する観光マップにも組み込んでいただきました。
「知りたい」と思ったときにすぐにアクセスできるのが魅力。ふと浮かんだアイデアや、ふっとわいた好奇心が冷めないうちに関連する論文を読めば、モチベーションは高まります。期待は、最新の論文はもちろんですが、十数年前の論文のオープンアクセス化。先行研究として参考にすることも少なくないため、実現すればさらに研究が進むはずです。