1 .他人に変えられるのではなく、自ら変わるために
教育は子どもの人生に深く関わる営みです。子どもを変えるには、自らを変えなければなりません。そのための知識やスキル(技能)は、教育史や教育基礎(教育原理)の知見に基づいてこそ生きて働くものとなります。
.JPG.jpg)
教育は子どもの人生に深く関わる営みです。子どもを変えるには、自らを変えなければなりません。そのための知識やスキル(技能)は、教育史や教育基礎(教育原理)の知見に基づいてこそ生きて働くものとなります。
.jpg)
教育は、地域や学校に根ざして個別具体的に営まれています。同時に、教育は社会と結び付き、グローバルに動いています。教育社会学やカリキュラム論・教育方法学の観点を通して、客観的かつ自省的に子どもの実態や教育課題を捉えるとともに、具体的な教育実践の方法論を身につけます。
教育は真空の中で行われるものではなく、教師の実践は教育システムと地域社会の現実の中で行われるものです。教育経営学や生涯学習論(社会教育学)を通して教育が受けている社会的制約を踏まえつつ、それを乗り越える知恵を修得します。
子どもの発達と教育の関係や、国家・社会と教育の関係を踏まえ、それらの知見を教育の目標・内容・方法に生かせるような教育実践のあり方を科学的に探求し、学びます。
| MON | TUE | WED | THU | FRI | 集中講義 | |
| 1・2時限 | 政治学 | 教育史特講 | 事前・事後指導 | |||
| 3・4時限 | 社会学 | 日本史概説I | 事前・事後指導 | 生涯教育演習 | ||
| 5・6時限 |
|
教育経営学演習 | 教育課程演習 | |||
| 7・8時限 | 教育方法学演習 | 教育人権アプローチ特講 | 生涯学習概論I | |||
| 9・10時限 | 中等教科教育法I | 哲学概論 |
3回生前期の一例

文献の講読や実践例の分析を通して、カリキュラムの基礎理論とその具体例を学びます。

教室環境整備と授業研究に関する演習を通して、教育実践に関する実践的知識と方法を学びます。
.jpg)
地域学習を事例に教育の歴史を学び、奈良の豊かな文化財を用いた授業づくりとフィールドワークに取り組んで、理論と実践の往還を考えます。
教育史特講・演習/教育哲学・思想特講・演習/教育社会学特講・演習/教育経営学特講・演習/教育方法学特講・演習/教育課程特講・演習/生涯教育計画特講I/生涯教育演習/教育人権アプローチ特講・演習/生涯教育史特講/校外学習指導特講/生涯教育政策特講
授業の詳細はシラバスからご覧いただけます。「教育学部 シラバス」から科目名を検索のうえ、ご覧ください。
私は高校生の頃、「教育に興味はあるけれど、どの教科を深めたいかまでは決まっていない」とずっともやもやしていました。そのような高校生時代に奈良教育大学の教育学専修の存在を知りました。さまざまな角度から教育について学ぶことができ、入学後に自分の関心を深めることができる自由さに魅力を感じました。
実際に入学してみると、教育についての考えは人それぞれであると気付かされることがたびたびありました。また、友達や先生との会話の中で、新しい視点をいろいろ知りました。教育についてたくさん学べることが、この専修のいいところです。
また、副免許も取りやすく、入学してから校種について再考しやすい点もこの専修の良さだと思います。
みなさんも僕たちと一緒に教育学専修で学びませんか?

2021年度作成(※所属や内容は作成当時のものです。)
小学校教諭一種 等
本専修の卒業生の多数が、学校の先生になっています。主に、小学校の教員ですが、中学校、高等学校や特別支援学校の教員になる人もいます。
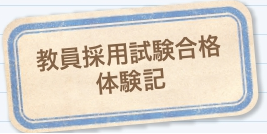
教員の研究内容や研究室などについて、広報誌等で紹介した記事をご覧ください。※所属および記事の内容は、作成当時のものです。
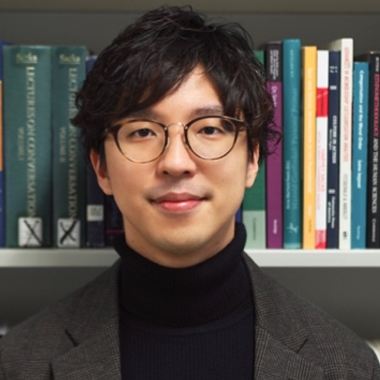 「静かにしてくださーい!」-授業場面の作られ方の社会学的考察-粕谷圭佑先生(E-book 2021年4月発行)
「静かにしてくださーい!」-授業場面の作られ方の社会学的考察-粕谷圭佑先生(E-book 2021年4月発行)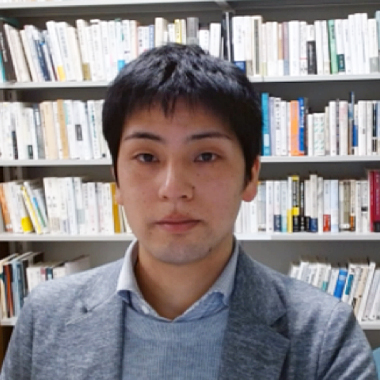 「教育における「豊かな体験」とは?-教育哲学からのアプローチ-」浅井健介先生(E-book 2022年4月発行)
「教育における「豊かな体験」とは?-教育哲学からのアプローチ-」浅井健介先生(E-book 2022年4月発行)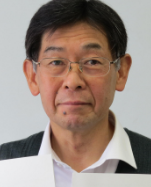 「学習の「主体性」と「地域」の自立志向との連動関係の探究」片岡弘勝 先生(奈良教育大学Knowledge リレーコラム2021年掲載)
「学習の「主体性」と「地域」の自立志向との連動関係の探究」片岡弘勝 先生(奈良教育大学Knowledge リレーコラム2021年掲載) 「地域を学び、地域で学ぶ」板橋孝幸 先生(広報誌「ならやま」2020秋号掲載)
「地域を学び、地域で学ぶ」板橋孝幸 先生(広報誌「ならやま」2020秋号掲載) 「グローバル時代の市民を育てるカリキュラム研究」橋崎頼子 先生(広報誌「ならやま」2015春号掲載)
「グローバル時代の市民を育てるカリキュラム研究」橋崎頼子 先生(広報誌「ならやま」2015春号掲載)※所属および記事の内容は、作成当時のものです。
教員の研究内容をもっと知りたい方は、下記表の教員氏名をクリックし、教員個人ページ内の「研究シーズ」をご覧ください。また、下記「研究シーズ」一覧からもご覧いただけます。「研究シーズ」とは教員の研究内容をA4一枚にまとめたものです。(WEBからお読みいただけます)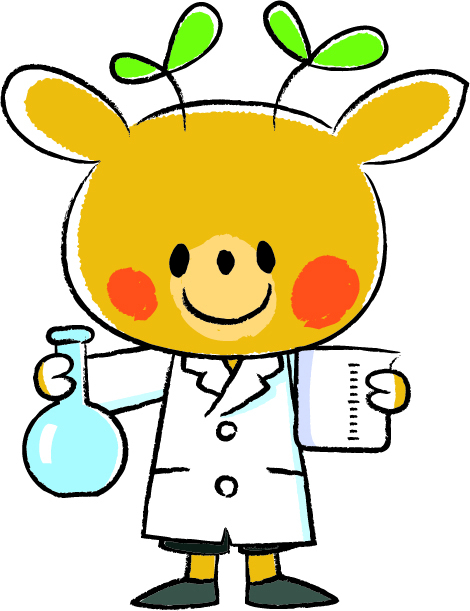 奈良教育大学 大学教員「研究シーズ」一覧はこちら
奈良教育大学 大学教員「研究シーズ」一覧はこちら
| 分野 | 職名 | 氏名 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|
| 教育学専修 | |||
| 教育学・教育史 | 教授 | 板橋 孝幸 | 近・現代における地域教育運動の研究 |
| 教育社会学 | 准教授 | 粕谷 圭佑 | 子どもの社会化、教育場面の相互行為に関する研究 |
| 生涯学習 | 教授 | 片岡 弘勝 | 地域生涯学習論研究、社会教育の原理的歴史的研究 |
| 教育課程・教育方法 | 教授 | 橋崎 頼子 | 市民性教育のカリキュラム構成原理に関する研究 |
| 教授 | 赤沢 早人 | 教育方法学、教育課程論 | |
| 教育哲学・思想 | 特任准教授 | 浅井 健介 | W・ベンヤミンの思想を手がかりとした教育思想研究 |
| 特任教授 | 生田 周二 | 人権教育、子ども・若者支援の社会教育的研究 | |